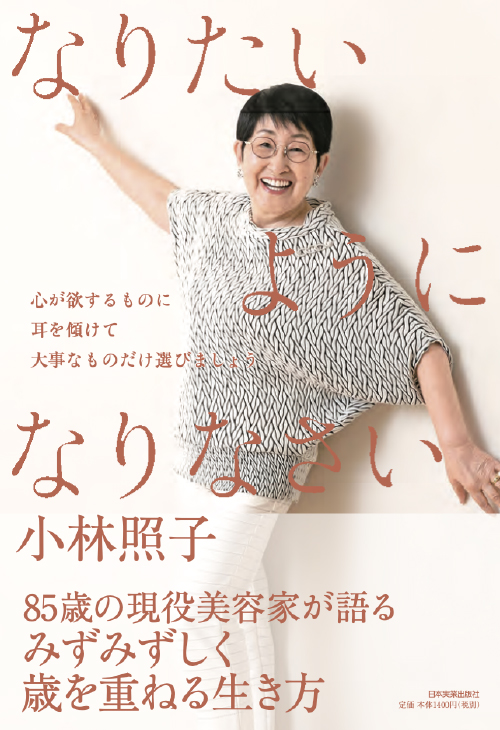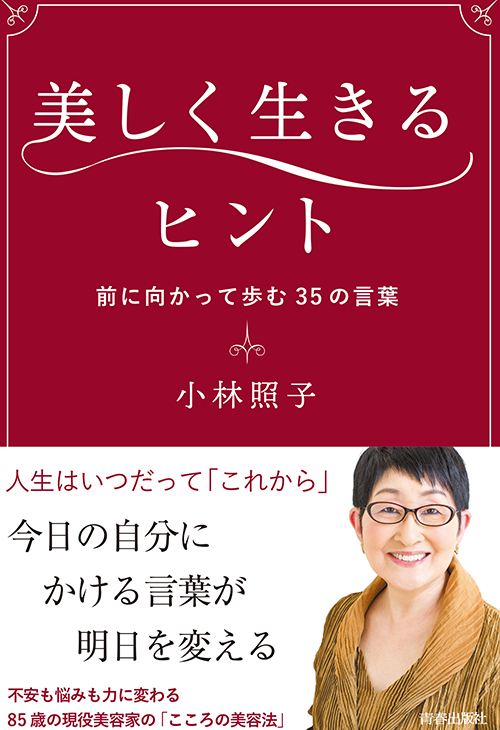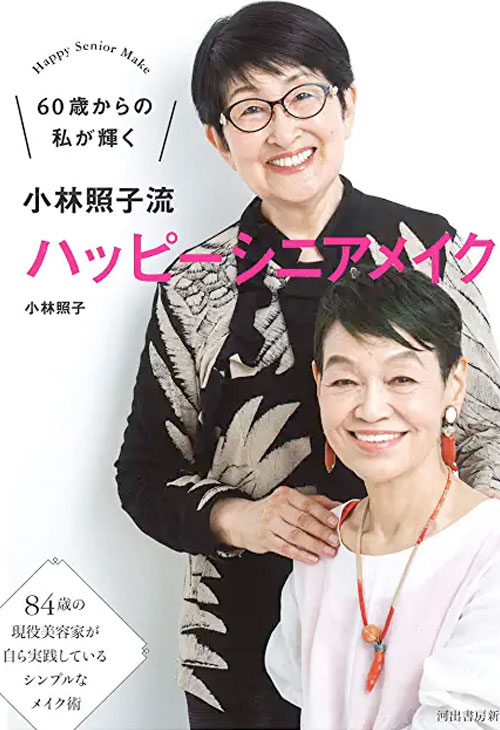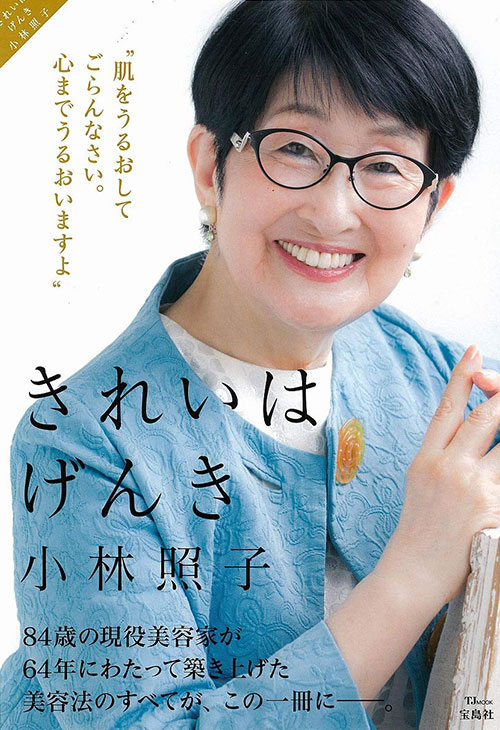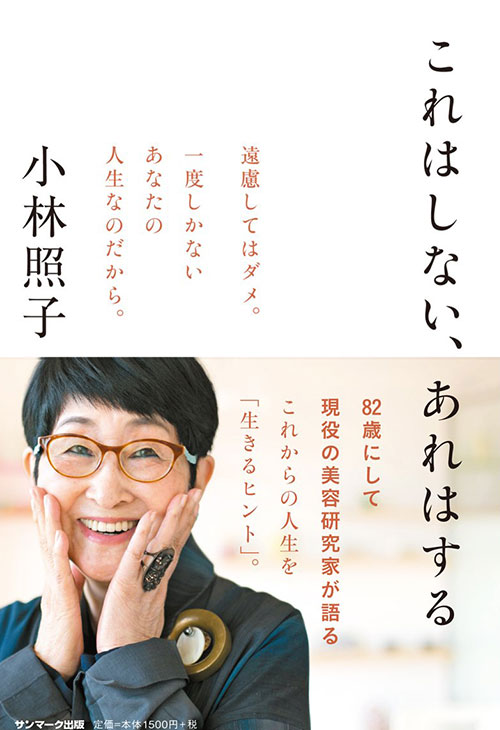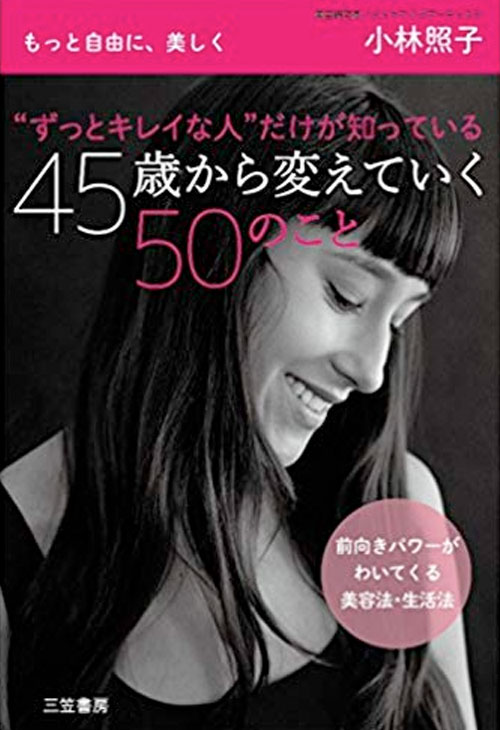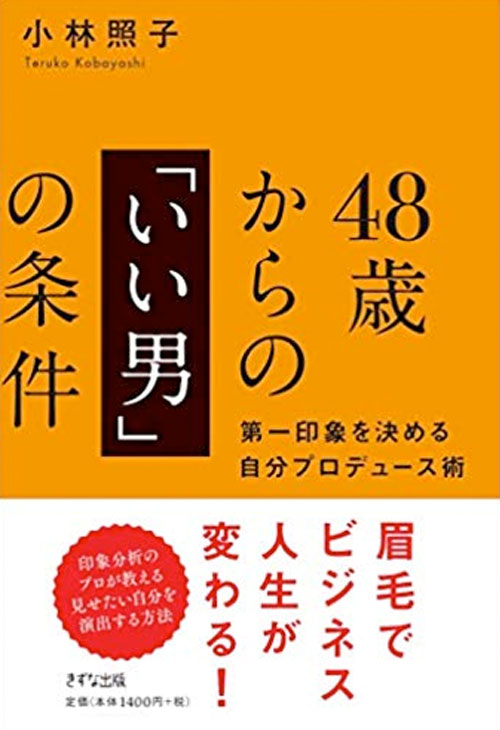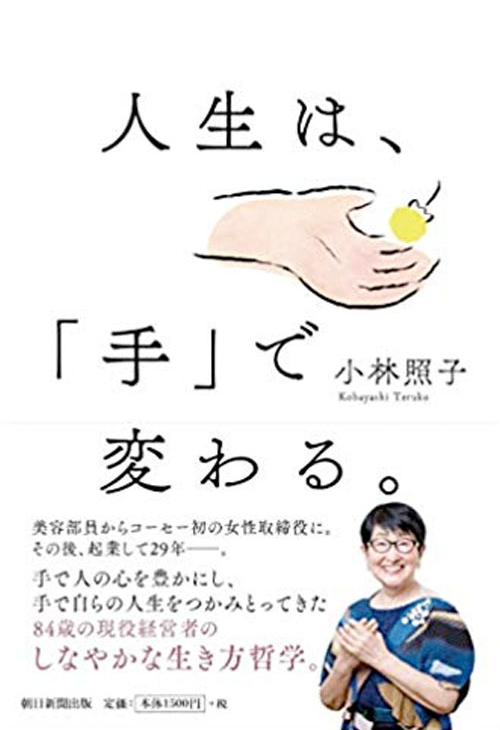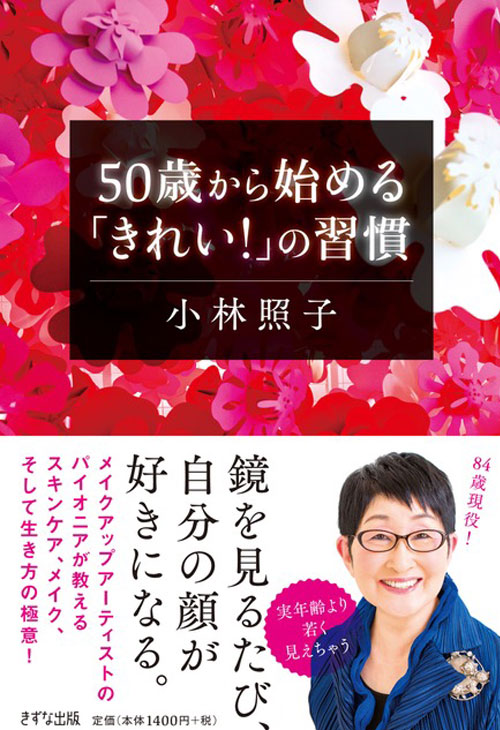講義レポート

第7期4月 惠美初彦先生による第1回目講義

4月9日(水)に行われた第1回の後半では、立志教育の第一人者・惠美初彦先生による講義がありました。
今回はその内容について、7期生の西村早織がご報告いたします。
<立志教育とは?>
「立志教育」
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、文字通り「志を立てる」ことを学ぶ教育です。
実はこの教育は、江戸時代初期からすでに存在しており、藩主の家系などでは代々の教育として受け継がれてきたそうです。
私自身、学校教育に携わる身でありながら、「立志教育」という言葉を耳にしたのは、初めてでした。
ですが、最近の学校現場でも、単に進学を目的とするのではなく、生徒一人ひとりが「自分の進路をどうつくるか」を考える重要性が語られるようになってきました。
そして私たち大人もまた、キャリアや働き方を見直す機会が増えています。
その根っこにあるべきものが「志」なのだと、今回の講義を通じて気づかされました。
では、「志を立てる」にはどうしたらいいのか?
私たちは全8回の講義を通して、自分の「志」に向き合い、言葉にするプロセスに挑戦していきます。
ATAの先輩たちからも後半になるほど、自分と向き合うことの大変さを感じるとの声も聞いています。
ですがあきらめずに自分の「志」に向き合い、12月の立志式では、自分の志を自信を持って語れるようになりたいです。
第1回の講義ではその導入として、「職志」「職系・職類」「和談」という3つの視点から、自分の働き方、人とのかかわり方について学びました。
<職志 〜人生理念はたった6つに集約される~>
先生によると、人が目指す「志」は6つに分類されるといいます。
①人の成長/ ②幸せの増進/③理想の社会実現/④社会に役立つ事業/⑤平和の前進/⑥文化の発展と調和
この「職志」は、いわば私たちが「なぜ働くのか?」という理由そのもの。手段は違えど、目指すところはこの6つのいずれかなのだということです。
しかも直感で選んだ志は、基本的には変わらないのだそう。
7期生は、①や②を選ぶ人が多かったところも印象的でした。
働くうえで悩んだとき、「私は何を目指しているのか」に立ち返れる軸として、この職志はとても大事な観点だと思いました。
<職系・職類 〜「自分の特性を活かした働き方」を知る~>
「どんなふうに働くのが自分に合っているのか」
そんな視点で働き方のスタイルを見つめ直せるのが、「職系・職類」という考え方です。
職系は、次の4つに分類されます。
・社長(独立・支援)
・幹部(帰属・支援)
・一匹狼(独立・前線)
・専門職(帰属・前線)
「上司を持つか/持たないか」「上司になるか/ならないか」という2つの軸で分類され、自分がどんな立場や関わり方を好むのかが見えてきます。
7期生の多くが「幹部型」に分類されたのは驚きでした。実は私自身もこのタイプで、今の仕事との親和性にも納得感がありました。
さらに職類は、「計算・科学・文芸・奉仕・音楽」など職業を10タイプに分類したもの。
ここから自分にあった職業が見えてきます。
自分が自然と惹かれるものや得意としてきたことが、実はこの職類に表れているのだと気づきました。
この「職系」と「職類」の視点を組み合わせていくことで、「自分の特性を活かした働き方」が見えてくるのだと思います。

<和談 〜批判しない話し合いという選択肢~>
最後は「和談」という、議論の進め方の基本となる考え方です。
私たちは話し合い=討論と考えがちですが、「和談」はまったく異なるアプローチ。対立ではなく、気づきを“足し合う”共同的な対話を目指します。
討論:意見を戦わせる/批判的/勝ち負け
和談:気づきを共有/探究的/発見と成長
実際、私自身も経験がありますが、チームでうまくいかないときほど、「お互いのせいにしたがる」など否定的な空気が広がってしまうこともあります。
でも「まず受け止める」「学び合う」空気があるだけで、前向きなエネルギーが生まれるのだと思います。
私が今回ATAに参加したのも、さまざまなフィールドで活躍する皆さんと共に学び合い、視野を広げたいという思いからでした。
まさにそのために、この「和談」というスタイルが大切だと感じました。
意見をぶつけ合うのではなく、お互いの背景や価値観を分かち合いながら、自分の視点を少しずつアップデートしていく。
そんな豊かな対話の時間を、7期のみなさんと一緒に育んでいけたら嬉しいです。


西村 早織