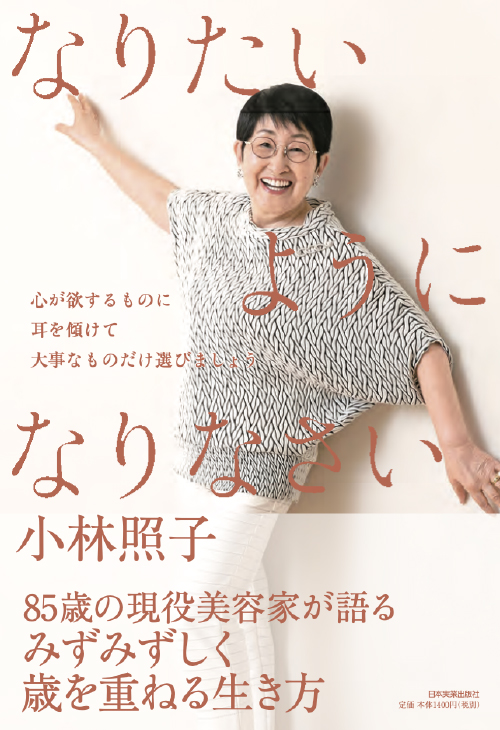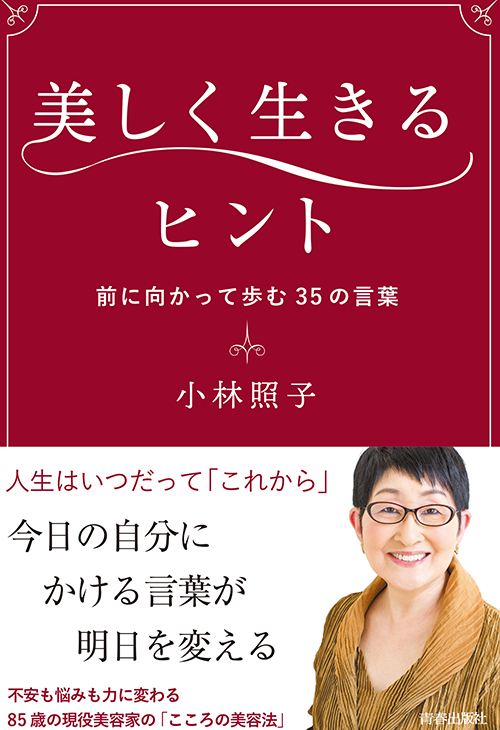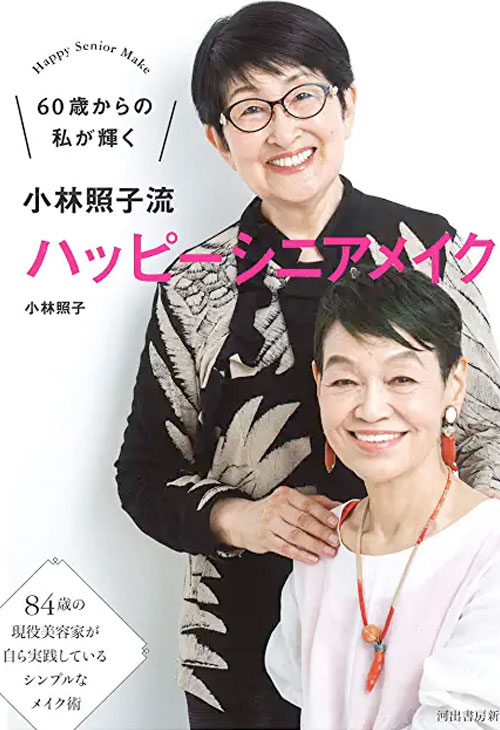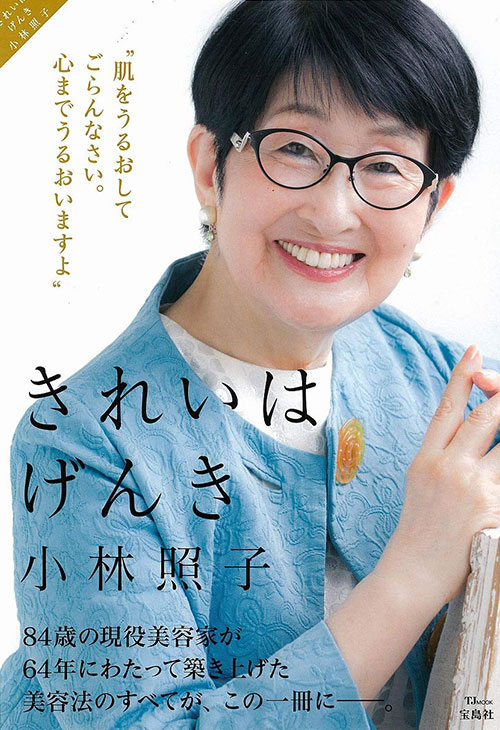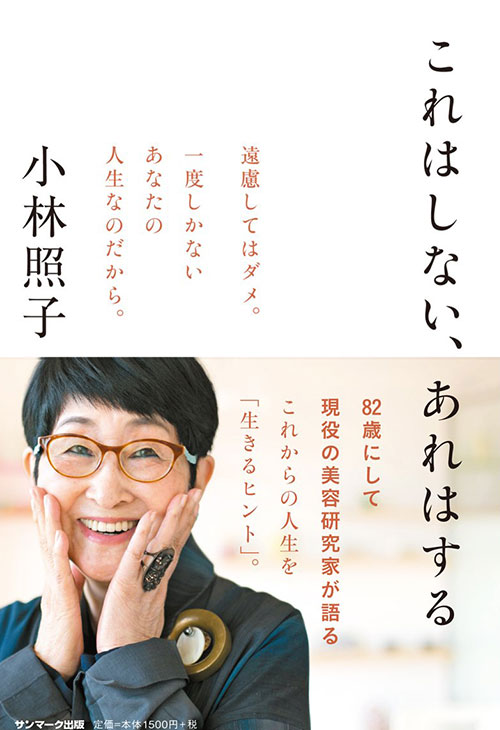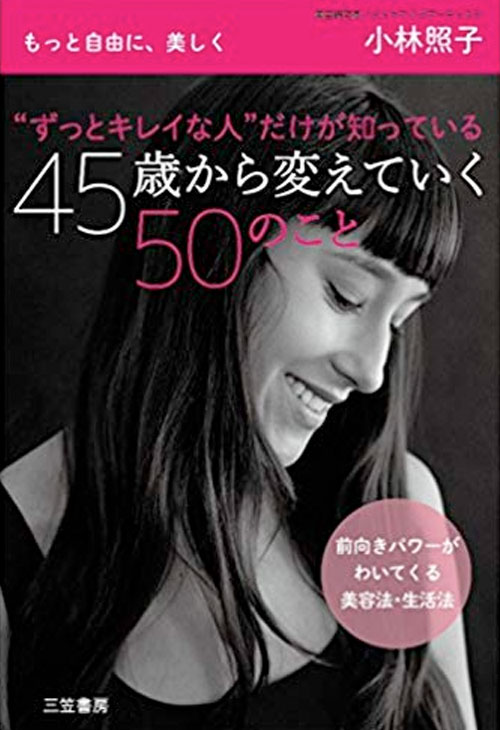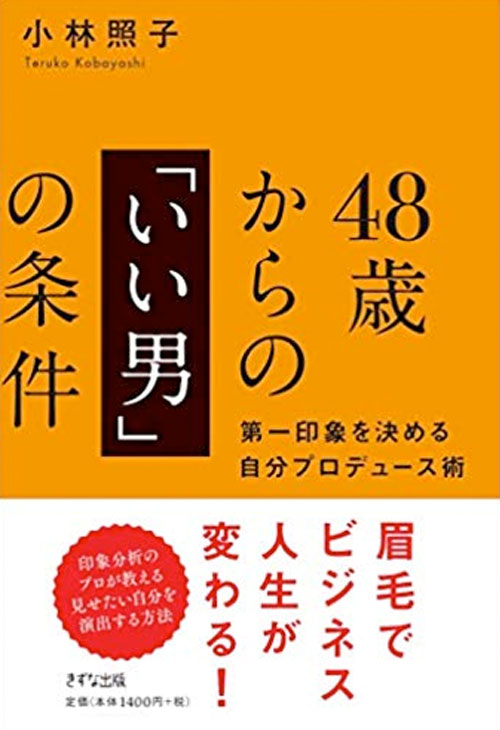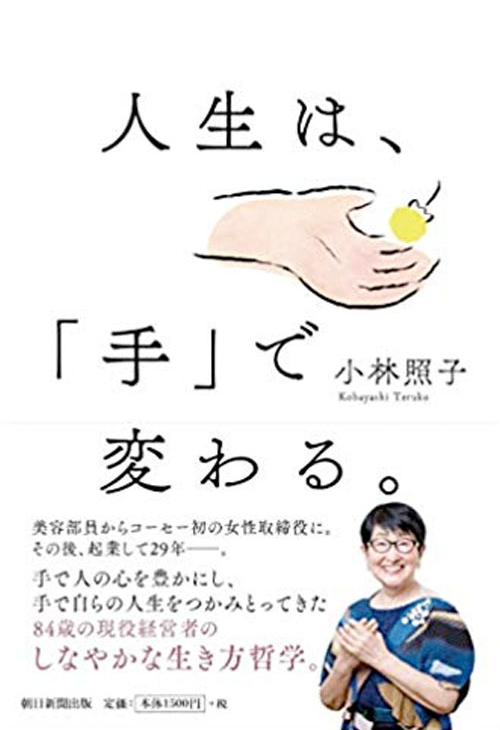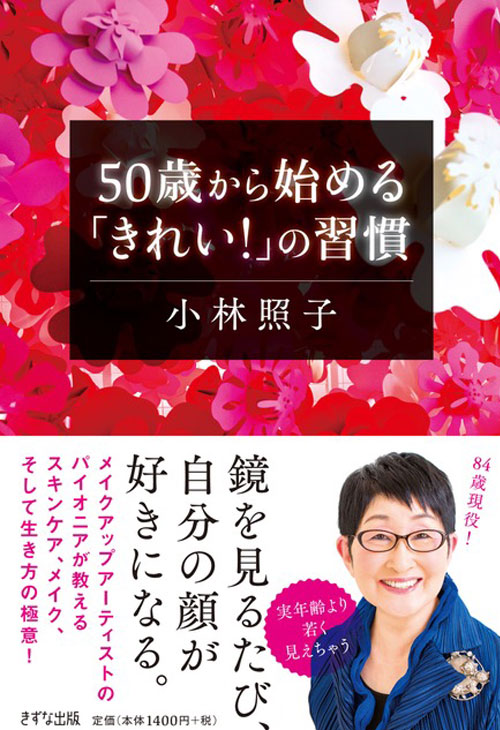講義レポート

第7期11月 惠美初彦先生による第7回目講義

11月6日(水)に行われた第7回目の講義『来果探求局面』では、これまで内省を重ねてきた理念を、5年後の具体的な目標として言語化し、その実現に向けた行程を設計する重要な局面となりました。
今回はアマテラスアカデミア7期生の山口星がレポートいたします。
15人それぞれの5年後への挑戦
今回の講義の核心は、7期生15人それぞれが描いた「5年後の目標」の発表でした。
女性のキャリアを応援するロールモデルになるという次世代への想い、プロダクトマネージャーとして新規プロダクトを作るというビジネスでの価値創造、日本の伝統工芸や地域文化を世界と次世代につなぐという文化継承の使命、理科教員として南極に行って南極授業をするという壮大な目標まで—。
同じ教室で学んできた仲間たちが、それぞれまったく異なるフィールドで、まったく異なる方法で社会に貢献しようとしている姿に、大きな刺激を受けました。
それぞれの発表と併せて描かれた「心象図」も印象的でした。循環する成長の矢印、木が実をつけていく図など、言葉だけでは表現しきれない志の構造が視覚化されていて、一人ひとりの想いの深さが伝わってきました。
私自身の5年後の目標を言語化する過程で、これまでの人生のターニングポイントを振り返りました。そのすべてに共通していたのは「好奇心」でした。好奇心がいろいろなところに私を連れて行ってくれた—その原動力を大切にしながら、これから先の5年間をどう生きるかを真剣に考える時間となりました。

惠美先生の実践例に学ぶ志の形
講義の中で惠美先生が語られた、ご自身の教育実践のエピソードが印象的でした。先生は以前、経済的な事情で進学が難しい生徒たちの大学進学を支援するという具体的な目標を掲げ、実際に5年間取り組まれたそうです。
一人ひとりに寄り添い、学習環境を整え、様々な支援を行いながら、最終的に多くの生徒を大学進学へと導かれた—その話を聞いて、志とは美しい言葉だけではなく、徹底的な実践と覚悟を伴うものだと実感しました。
「一灯を下げて暗夜を行く」という生き方
講義の終盤で惠美先生が紹介された言葉が、とても心に残りました。
「一灯を下げて暗夜を行く」
これは作家の小島直樹氏が書いた言葉で、人生という見通しの立たない道を歩むとき、たくさんの灯りではなく、たった一つの灯火を掲げて進むことの大切さを表しています。そしてそして古くから伝わる「一隅を照らす、これすなわち国宝なり」という教えへと繋がります。
一人ひとりが自分の持ち場で精一杯輝くこと。それが集まれば、国全体が輝く—。
私自身、これまで好奇心に導かれて色々なことに挑戦してきましたが、私の「一灯」は何なのかを深く問い直すきっかけになりました。そして、今日発表を聞いた15名それぞれが異なる分野で「一隅を照らす」存在になることで、社会全体に大きな影響を与えていく—アマテラスアカデミアという場の意義を、強く実感しました。
志を持つ仲間と歩む意味
次回最終講義では、一人ひとりが「5年後の目標達成の実行計画表」を発表します。15人分を印刷して配布し合い、お互いの志と計画を共有する仕組みになっています。

この「見える化」と「相互支援」の設計が素晴らしいと感じました。自分一人で目標を立てるのではなく、志を同じくする仲間たちと共有し、お互いに励まし合いながら進んでいける環境—これがアマテラスアカデミアの大きな価値だと思います。
この1年間、強み設定から理念設定、そして来果探求まで、段階的に自分自身と向き合ってきました。時には苦しく、答えが見つからない日もありましたが、同期という仲間がいたからこそ、ここまで歩んでこられました。
次回、15人それぞれが「一灯を下げて暗夜を行く」決意を発表する立志式が、今から楽しみです。

山口 星