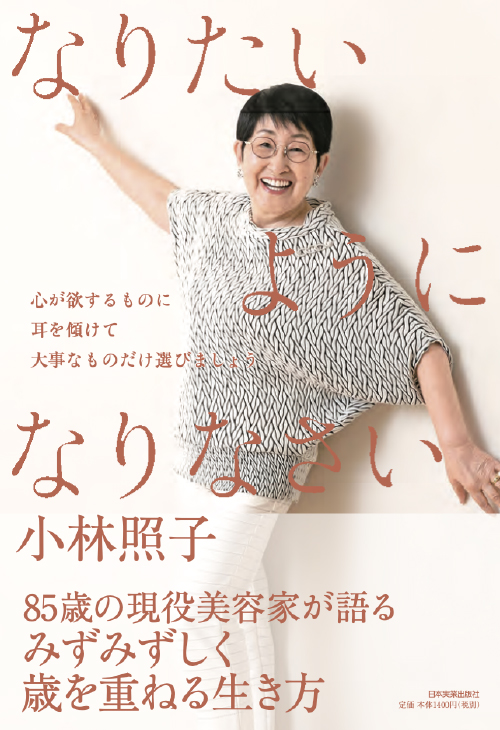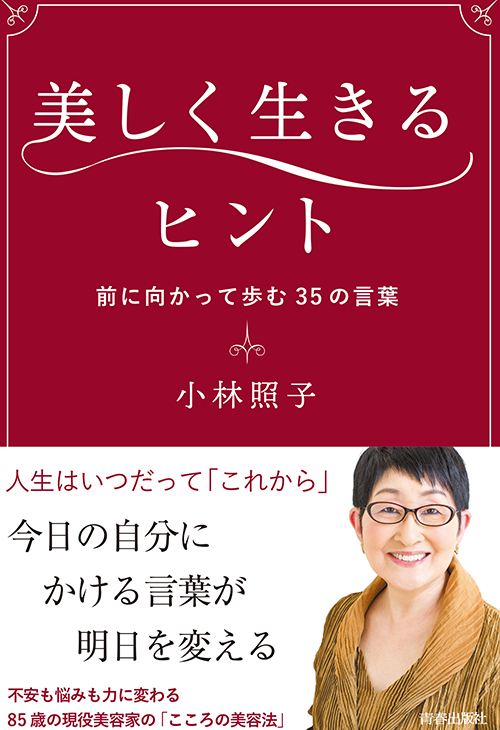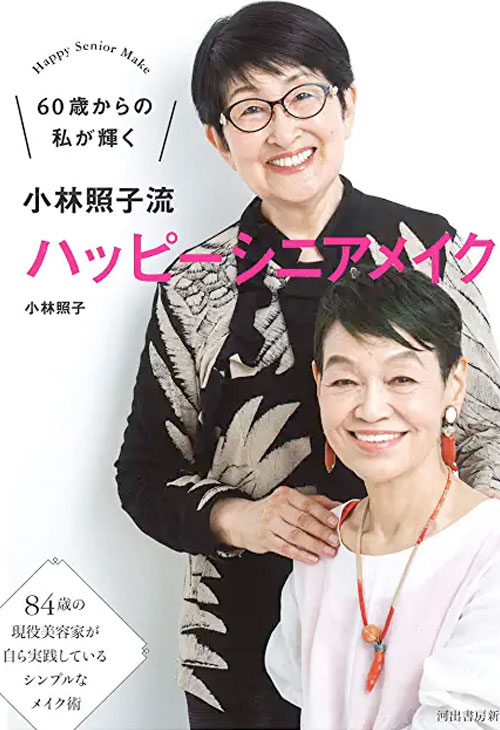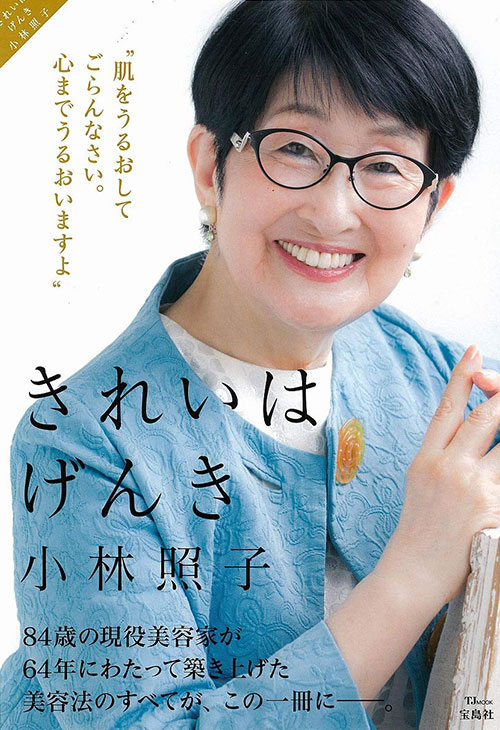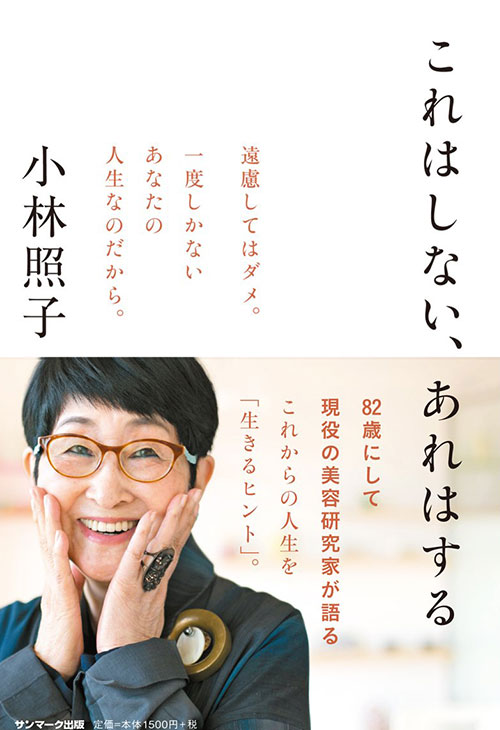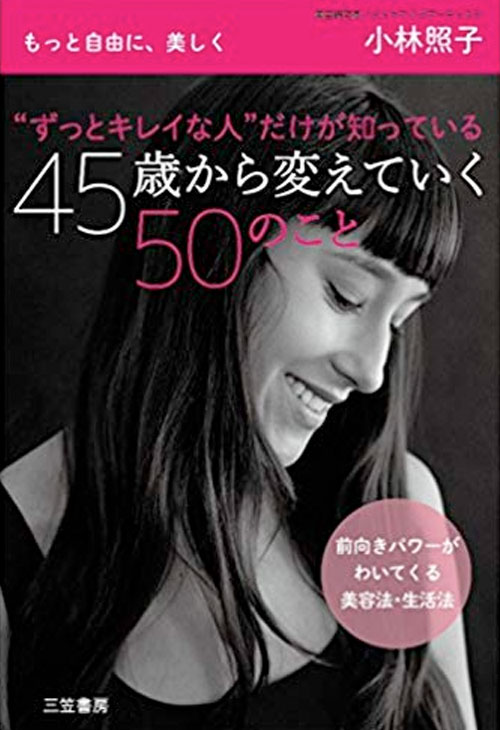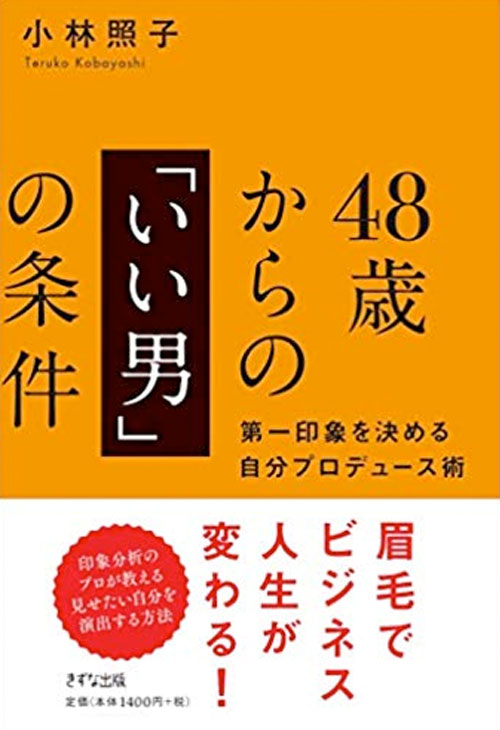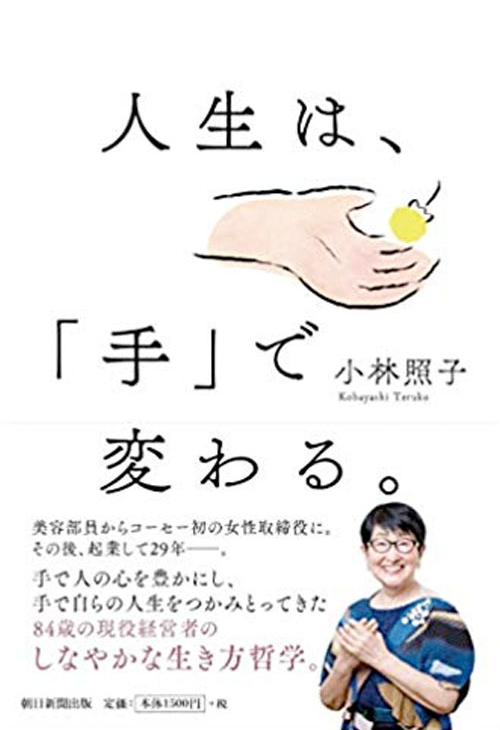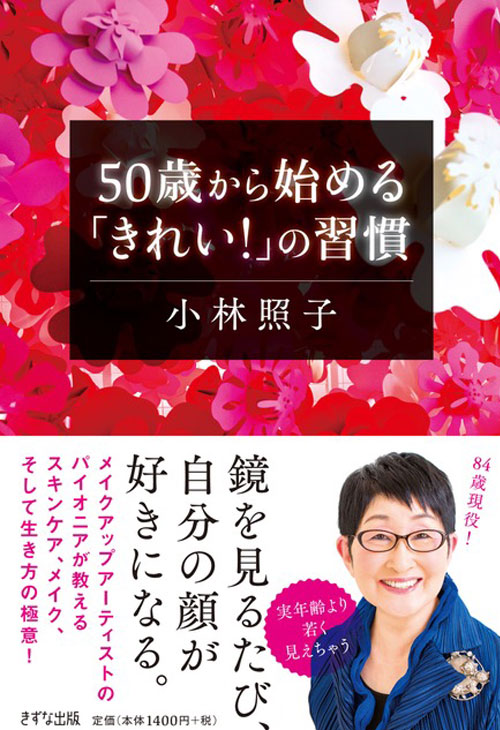講義レポート

第7期5月 惠美初彦先生による第2回目講義

「時代を超えて受け継がれる“志”から学ぶ、リーダーとしての在り方」
5月7日(水)に行われた第2回目の講義では、立志教育の第一人者・惠美初彦先生による、「先人の志」をテーマに学びを深めました。
恩田木工、上杉鷹山、二宮尊徳、坂本龍馬、西郷隆盛という5名の偉人の言葉や行動に触れ、彼らの言葉や生き方を通じて、その志が周囲に与える影響や、リーダーとしての在り方について深く学ぶ機会となりました。
時代を超えて受け継がれる価値観や人間性に触れる、深い学びの時間となりました。

〈利他の心〉が導く信頼と共感のリーダーシップ
講義を通じて特に印象に残ったのは、「利他」と「利己」の違いでした。
歴史に名を刻む偉人たちは、自分の利益よりも他者や社会の幸せを優先する姿勢を貫いており、その行動が、周囲の信頼を集め、結果的に多くの人の心を動かしていたことが、心に残りました。
現代に生きる私たちが「志」を持って生きるとは、まさに利他の視点を持ち、誰かのため、社会のために何ができるかを考え行動すること。これがリーダーとしての本質の一つだと学びました。
〈心田を耕す〉 内面を磨くというリーダーの責任
「心田を耕す」という言葉にも深く共感しました。
知識やスキルだけではなく、自らの内面を問い続け、正しい判断軸を持ち続けること。
特に不確実性が高まる現代においては、「人として正しいかどうか」を基準に行動を選択できる力が問われていると実感しました。
そして、日々の小さな選択の積み重ねのなかで、その問いを持ち、実践し続けることが、リーダーに求められる姿勢なのだと教えられました。
〈和談の姿勢〉誰一人取り残さない合意形成
恩田木工が大切にした「和談」の姿勢にも強く心を動かされました。
まさに、今回の講義では、メンバー一人ひとりの発表から、自分一人では得られなかった気づきや学びにつながることを体感し、まさに「和談」が生み出す価値を体感しました。
立場や価値観の違いを超え、対話を重ねることで全員の納得感をもって物事を進める姿勢は、多様性が求められる現代のチームや組織において、重要な指針になると感じました。

志があるから、迷わずに進める
今回の講義を通じて、「困難なときこそ、志が羅針盤になる」という言葉の意味が、より実感を持って心に響きました。
仕事や家事に追われ、忙しく過ごす日々の暮らしの中では、迷いや不安が生まれる場面も少なくありません。
そんなときに、自分が何を大切にし、どんな未来を目指しているのかという“志”が明確であれば、たとえ道が見えなくなったとしても、方向を見失わずに前へ進めると感じました。
また、志は個人の想いで終わるものではなく、共感を呼び、人を巻き込み、仲間と共に形にしていくものでもあることもわかりました。
今回学んだ偉人たちのように、自らを律しながら、仲間との信頼と対話を大切にする姿勢こそが、周囲を動かす真のリーダーシップにつながると学びました。
今後は、より長い視点で物事をとらえる意識を持ち、自分一人では実現できないようなことでも、志やビジョンをしっかりと言葉にし、共感してくれる仲間と「和談」の姿勢で進めていくことを心がけていきたいです。

山口 夏生